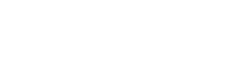Profile
画家デビュー
芸大卒業後も就職はせず大学院の前身であった専攻科へ進み、奈良県の公立中学高校の美術科非常勤講師をしながら芸大のアトリエで制作をつづける。
専攻科1年目には若手作家の登竜門的なコンクールであった日動画廊の昭和会展に入選し招待作家となる。
しかしその後、父が仕事で連帯保証人になっていた不運から自己破産。
翌年も昭和会展に入選したことで賞審査のための制作に取り掛かろうとしていた矢先、夜逃げ同然に奈良を離れて家族ともども大阪府羽曳野市の賃貸住宅に引っ越しする。
弓手家が財産を失い、私は中学の非常勤講師と警備員のアルバイトを掛け持ちして学費を捻出。出品活動を続けることも厳しい状況であったが、この昭和会展への出品が画家になれるラストチャンスと考え、危機的状況であった家族の了解を得ながら背水の陣で制作に取り組む。
1997年、「捌かれる構図」(F50号)を第32回昭和会展に出品し、日動美術財団賞を受賞する。移り住んだ土地で生肉の解体場を取材し、人間の根源的な生への営みをストレートに問う作品を制作した。(笠間日動美術館蔵)
専攻科修了後は高校の非常勤講師をしながら画家活動をつづける。
教師時代には後に映画監督となる塩崎祥平が教え子となったことも運命的な出会いであった。彼とは後に再会し、私が映画作りに関わることに繋がっていく。
1999年、29歳の時に日動画廊での個展を開催し、本格的に画家としての生活が始まる。
当時の作品は“狩をする人”や“船を作る人”など、受賞作に連関した人間の根源探究に基づいたものが多く、土色基調の厚塗りの絵肌が特徴であった。
初めての海外旅行でラスコー壁画を取材するなど、実地調査も精力的に敢行。
初個展の年に高校美術部の1年後輩と結婚する。
結婚後、妻の地元でもある奈良に戻り、絵画教室を掛け持ちしながら生計をたてつつ、日動画廊を中心に個展や発表活動を続ける。
2002年に長男、2004年に次男、2007年に三男が誕生。
作品は以前の狩猟民族的な視点から農耕民族へと移行し、現在のコンセプトに直結する「土」と向き合うテーマが醸成される。作品には“耕す人”や“牛”などが登場し始める。原点主義とも言える日本人の足元を見つめるテーマへの意識が深まり、耕すような下地作りもこの時期から強くこだわるようになる。